腰痛診断の鍵!腰部診察の重要ポイントと実践テスト
腰痛は、人生で80%以上の人が経験すると言われている一般的な症状です。腰椎は二足歩行のために前弯が形成され、下位腰椎には前方へのせん断力が加わるため、腰痛の原因となりやすい部位です。正確な診断と適切な治療のためには、丁寧な診察が不可欠です。このブログ記事では、腰部を診察する際の重要なポイント、解剖学的な特徴、および診断に用いられる主要なテストについて詳しく解説します。
1. 診察の進め方と視診のポイント
診察は、患者さんが診察室に入ってくる時点から始まります。
- 歩行状態の観察:
- 歩様: 患者さんの歩き方を注意深く観察します。腰椎に過度の狭窄がある場合、患者は直立できず、前かがみの姿勢で歩行する傾向があります。これは、椎間板の後方への膨隆や黄色靱帯の前方へのまくれ込みによる神経根や馬尾への圧迫を軽減するためです。
- 膝の伸展位歩行: 膝が伸展したままの歩行でないかを確認します。
- 補助具の使用: 壁伝いに歩いているか、人に支えられているかなども観察します。
- 姿勢の観察:
- 発赤や発疹: 皮膚に帯状ヘルペスのような発赤や発疹がないかをチェックします。
- 皮膚の異常: 数個のカフェ・オ・レ斑(café-au-lait spot)があれば神経線維腫症を、腰仙椎中央部の脂肪腫や毛髪の密生があれば三分脊椎症を疑います。
- 脊柱のアライメント:
- 前弯・後弯: 側面から見て、腰椎に緩やかな生理的前弯があるかを確認します。過度の前弯は股関節屈曲拘縮によることがあります。骨粗鬆症による腰椎圧迫骨折では、腰椎の後弯が著明になることがあります。
- 側弯症: 構築性側弯症の診断は視診が重要です。肩の高さ、肩甲骨の高さや隆起、ウエストラインの非対称、前屈時の肋骨隆起や腰部隆起がないかを観察します。疼痛性の側弯症は椎体の回旋を伴わず、脇線の非対称が診断の手助けとなることがあります。
2. 腰部の解剖学的部位と触診
- 後方部の触診:
- 棘突起: 腰椎の後正中線に沿って触知します。正常では直線的に並んでいますが、外傷による椎間関節の脱臼や棘突起の骨折で偏位することがあります。L7とT1の棘突起は上位の棘突起よりも大きいです。
- 棘上靱帯・棘間靱帯: 棘突起の間にある靱帯を触診し、圧痛や欠損がないかを確認します。
- 傍脊柱筋: 棘筋、最長筋、腸肋筋からなる傍脊柱筋の最表層を触診します。異常があれば、筋緊張の亢進(鋼様硬)、萎縮、左右の大きさの違い、圧痛などを確認します。
- 腸骨稜: 腰のくびれ部分に沿って触知できる凸状の骨隆起線です。その最上部はL4とL5の棘突起間に相当します。左右の高さの違いは骨盤の傾斜を示唆します。
- 殿筋群の起始部: 腸骨稜のすぐ下にある殿筋群の起始部を触診し、線維脂肪性の結節や殿皮神経の神経腫がないかを確認します。
- 上後腸骨棘(PSIS): 腸骨稜の後内側にある骨隆起で、多くの場合は殿部のくぼみに一致します。左右の上後腸骨棘を結んだ線は、仙腸関節の中心、またはS2棘突起の高さに一致します。この部位は靱帯損傷や腰部の捻挫による痛みが好発します。
- 坐骨結節: 殿溝(殿部と大腿後面の間にある深い横走する溝)の中央部にある骨隆起です。股関節を屈曲させると大殿筋が上方へ移動し、触れやすくなります。
- 大転子: 股関節を内旋・外旋させながら触知すると確実です。
- 坐骨神経: 坐骨結節と大転子の中間を通っています。股関節屈曲位で強く圧迫すると、皮下脂肪の下に触れることができます。梨状筋症候群では圧痛を生じることがあります。
- 前方部の触診(仰臥位、膝屈曲位):
- 臍: L3-L4椎間部に位置し、この高さで大動脈が総腸骨動脈に分岐します。
- 椎体前面: L4、L5、S1の椎体前面を触れることができます。L5-S1間の仙骨岬角(sacral promontory)は、この領域で最も突出しています。
- 大動脈: L3/4椎間部で拍動を触知できます。
- 前腹壁の筋: 腹筋群を触診し、筋力低下や筋の欠損がないかを調べます。
- 鼠径部: 腸腰筋膿瘍がないか、鼠径ヘルニアやリンパ節の腫大がないかを調べます。
3. 関節可動域テスト
腰椎は胸椎と異なり肋骨の付着がないため、より大きい可動域を示します。関節突起が矢状面に近いため、特に屈曲・伸展角度が大きいです。
- 屈曲: 患者に膝関節を伸展したまま前屈させ、指先と床との距離を測定します(Finger-to-floor distance)。腰椎の前弯は屈曲によって平坦になる程度で、頸椎のように後弯を生じることはありません。
- Schoberテスト: 腰仙部の2点間隔が前屈時にどれだけ増加するかを測定します。通常4〜5cmの増加が正常とされます。
- 伸展: 患者の腰に手を当て、可能な限り後屈させます。脊椎すべり症がある場合、伸展によって痛みが悪化することがあります。
- 側屈: 患者の骨盤を固定し、体幹を左右に傾けさせます。回旋が必ず伴います。
- 回旋: 患者の骨盤を固定し、肩をつかんで体幹を回旋させます。左右の回旋角度を比較します。
4. 神経学的検査
腰椎の病変は、しばしば下肢に反射、知覚、筋力の変化として現れるため、下肢全体を含めて行います。
- 筋力テスト(徒手筋力テスト:MMT): 筋力は0〜5で評価し、3+が「重力に抗して全可動域を動かせ、かつ最終肢位を軽い抵抗に抗して保持できる」ことを意味します。
- L4: 前脛骨筋(足関節背屈・内がえし)。
- L5: 長母趾伸筋(母趾背屈)、長趾伸筋(足趾背屈)。中殿筋(股関節外転)。
- S1: 長・短腓骨筋(足関節底屈・外がえし)。大殿筋(股関節伸展)。
- S1, S2: ハムストリングス(膝関節屈曲)。下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)(足関節底屈)。
- S2, S3, S4: 足内在筋(足趾の変形から評価)。
- 知覚テスト(皮膚分節:Dermatome):
- L4: 膝の前部、下腿内側、足部内側(脛骨稜の内側、内果、足部内側部分)。
- L5: 下腿外側(脛骨縁の外側)、足背部。
- S1: 足部外側、足底部(外果、足部外側)。
- S2, S3, S4: 肛門周囲(同心円状)。
- 反射テスト:
- 膝蓋腱反射(L2, L3, L4): L4が中心。
- アキレス腱反射(S1, S2): S1が中心。
- 表在反射(上位運動ニューロン): 腹皮反射(T7-L1)、挙睾筋反射(L1, L2)、肛門括約筋反射(S2, S3, S4)、球海綿体反射(S1, S2, S3)。
- 病的反射(上位運動ニューロン): バビンスキー反射、オッペンハイム反射、チャドック反射。
5. 特殊検査
腰椎疾患の診断には、これらの特殊な検査も役立ちます。
- 下肢伸展挙上テスト(SLRテスト):
- 仰臥位で膝を伸展したまま股関節を屈曲させ、坐骨神経の伸展による疼痛を誘発します。腰椎神経根の圧迫を示唆します。
- 交叉性SLRテスト: 健側のSLRテストで患側に痛みが生じる場合、より責任病変が疑われます。
- フリップサイン(Flip sign): 心理的因子があるかを確認するテストで、SLRテストが困難な患者で、膝関節伸展時に体幹が後屈しない場合は精神的要素が疑われます。
- 大腿神経伸展テスト(FNST): 腹臥位で膝関節を屈曲し、股関節を伸展させ、上位腰椎神経根(L2, L3, L4)の圧迫を調べます。
- Kernigテスト: 脊髄を伸展させ、疼痛を再現します。頸椎を前屈させた際に腰や下腿に痛みが生じる場合、髄膜刺激症状や神経根病変を示唆します。
- Valsalva手技: 患者に排便時のようにいきませ、脊髄腔内圧の上昇による背部痛や下肢への放散痛を誘発します。
- Milgramテスト: 仰臥位で下肢を伸展したまま約5cm挙上させ、硬膜内・外病変による脊髄腔内圧上昇の有無を調べます。
- Patrickテスト(FABERテスト): 股関節を屈曲、外転、外旋させ、股関節や仙腸関節の病変を調べます。
- 梨状筋テスト: 股関節を屈曲・膝関節を屈曲した仰臥位で、大腿と膝を内転方向に押す際に痛みが生じれば、梨状筋による坐骨神経の絞扼を疑います。
- Beevorサイン: 腹直筋の下方部分の麻痺を調べ、胸髄レベル(T10-12)の横断性病変を示唆します。
これらの詳細な診察とテストを組み合わせることで、腰痛の原因を正確に特定し、患者さんにとって最適な治療計画を立てることができます。
.png)

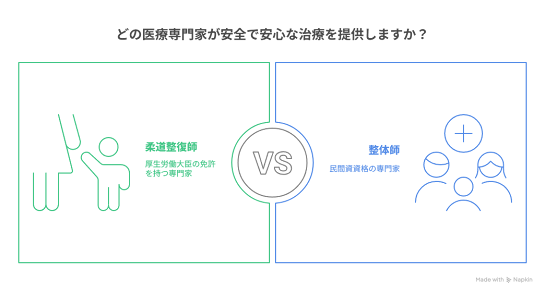

コメント
コメントを投稿